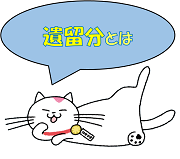特別受益とは
今回は「特別受益」について
本来ならば前々回に記述した「寄与分」の後でしたね。
特別受益とは
Aさんには、二人のお子さんがいます。
Aさんは、長男Cに自宅購入資金として1000万円を生前に贈与しています。
そして、Aさんは2000万円の財産を残して死亡しました。
相続人は、長男Cと次男Dです。さて相続関係はどうなるでしょうか?
ここで問題になるのは、Cが生前に受けた住宅購入資金です。
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。
そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。
このことを特別受益の持ち戻しといいます。
民法903条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
特別受益者に該当する者は
特別受益者となるのは、共同相続人に限られます。
上記の例の場合、長男Cは贈与の時点では推定相続人です。
もし、相続時にCが亡くなっていても、Cの代襲相続人であるCの子E(つまりAの孫)は、特別受益者となります。

しかし、例えばAが長男Cでは無くて、直接に孫Eに贈与していた場合、贈与時は推定相続人ではないので、特別受益者にはならないことになります。
贈与を受けた第三者も当然に特別受益者とはなりません。
贈与の内容
贈与の内容については次のとおりです
婚資
持参金や支度金など婚姻(養子縁組)のために被相続人から支出してもらった費用をいいます。
婚資は、原則として特別受益に該当します
ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。
結納金、挙式費用については、実務上確立した扱いがありませんが、特別受益に該当しないと考えられています。
高等教育のための学資
原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえます。
留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。
しかし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合は、特別受益には該当しないと考えられています。
事例の住宅購入資金は、生計の資本なので当然に該当することになります。
算定方法
事例の場合、特別受益の持戻しをした場合の相続分は次のとおりです。
(相続開始時の相続財産価額) + (贈与価額) =みなし相続財産額
2000万円 +1000万円=3000万円
長男C=3000万円×1/2(法定相続分)=1500万円-贈与額1000万円=500万円
次男D=3000万円×1/2(法定相続分)=1500万円
2000万円の相続財産の分割基準は、長男500万円、次男1500万円となります。
ところで、生前贈与が2000万円で、相続財産が1000万円の場合は、どうなるのでしょうか?
みなし相続財産は、3000万円でC、Dともに相続分は1500万円ですが、
Cはそれ以上の2000万円の贈与を受けています。
一方Dの相続分は1500万円も、残存する財産は1000万円しかありません。
この場合は、Cの超過分=Dの不足分の500万円が問題となりますが、
遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
ので、Cは0円、Dは1000万円となり、不足分の500万円についてCが補てんする必要ありません。
(相続開始時の相続財産価額) + (贈与価額) =みなし相続財産額
1000万円 +2000万円=3000万円
長男C=3000万円×1/2=1500万円-贈与額2000万円=△500万円=0円
次男D=3000万円×1/2=1500万円-不足分500万円=1000万円
持戻しの免除
特別受益の持戻しは被相続人の意思を推測し、相続人間の公平をはかるものといえます。
そのため、被相続人が自らの意思で持戻しを免除する場合には、遺留分の規定に反しない限り、持戻しはなされないことになります。
特別受益財産は、相続開始の時点を基準として評価されます。
相続開始時点の評価で具体的相続分を確定することができ、安定性がありしかも一部分割や遺留分算定も統一的に解することができて便宜であること、寄与分制度とのバランスなどが、その根拠とされています。
最後に、
遺産分割協議の際、特別受益に該当するものがあると思われる場合、
受益者(ここでいうC)は、Dに対し、なんらかの配慮を考えて協議に臨むこと、
逆にDは、Cの特別の受益を少しだけ意識して協議に臨むこと、そんなことが必要かと思います。
バランス、折り合いをうまくつけることが、大切です!
また、被相続人は一方に特別の受益を行ったと推定される場合は、遺言でしっかりとした意思表示をし、不要なトラブルを回避する手段を講じるべきかと考えます。
特別受益の持戻しや免除については「遺留分」との関係を切り離して考えることができません。
従って次回は、この「遺留分」についてお話ししたいと考えています。